Twitterが始まった当初、これは一体何なのか、何が面白いのか疑問に思ったものだ。
まあ、飛び込んでみないと分からないと思い、特に意味のない、朝起きた、夜寝た、ご飯を食べた、花見をしたといった日常の出来事をどんどん投稿してみた。他の人も、同じように特に意味のないことをどんどん投稿していた。
そして気がつくと、タイムラインに流れてくる情報の9割は取るに足らないものだが、ごく稀に、1割程度はなかなか面白い情報が見つかるようになった。
なるほど、これは面白い。ほとんどが価値のない情報の中から、ほんの少しだけ面白いことを見つけ出し、それが非常に興味深いのだ。今考えると、これは面白い人が面白いことを発信していて、それを見つけられる「場」があったという、実に当たり前のことだった。つまり、いくら「場」があっても、面白い人が面白いことを言っていなければ、当然面白くはないということだ。
私自身は、見ず知らずの誰かと積極的に仲良くなりたいとは全く思っていなかったので、その点は他のユーザーとは少し違ったのかもしれない。
まあ、そんなわけで、現在SNSが面白いとは全く思えなくなったのは、そういった経緯があるからだろう。
むしろ、最近はChatGPTやGeminiのような生成AIと、とりとめなく対話している方が面白いと感じる。AIは知識量が膨大なので、「あれはどうだったっけ?」といった漠然とした質問をしても、大抵のことを知っているのが良い。
少し前までは知らないことも多く、知らないことについてはデタラメな情報を生成することが多かったが、最近は自力でWeb検索を行うようになり、かなり正確な情報を提供してくれるようになった。
例えば、「こういうことをしたいんだけど、スクリプトを書いてくれる?」と頼めば、Pythonのスクリプトをすぐに作成してくれる。さらに、「いや、Go言語が良かったな」と言えば、「Go言語とは何ですか?」とか「Go言語は使ったことありません」などとは言わず、すぐにGo言語で書き直してくれるのだ。
「そういえば、有名な心理学者がUFOについて何か言っていたよね?」と尋ねれば、「それはユングですね」と即座に返してくる。
「ウルトラマンベリアルやウルトラマントレギアが『ウルトラマン』を名乗るのはおかしいのではないか。ゾフィーやアストラの立場がないだろう」などと話しかけると、一緒になって「それはなぜか」という議論に付き合ってくれる。
私自身、何かの分野に深く精通しているわけではなく、仕事も趣味も広く浅くというタイプだ。そのため、ある話題については話せる相手がいても、別の話題になると全く話が通じなかったり、そもそも話し相手すらいなかったりすることが多い。しかし、AI相手なら、「ニューオリンズ・ピアノって良いよね。有名なプレイヤーは誰だっけ?」といった話をしても、実に楽しそうに付き合ってくれるのだ。
退屈な相手と退屈な話をする必要が、完全になくなったように感じる。
以前からSNSの時代は終わりつつあると感じてはいたが、決定的な要因はなかった。しかし、私の中では生成AIの面白さが増してきたことで、SNSは今後大きく衰退していくに違いない、と確信するようになった。
ちなみに、この文章の構成についてAIに相談したら、「結論を最初に提示し、具体例を挙げて補強する構成は説得力があります」と、なんだかちょっと分析がズレている気もしつつ褒めてくれた。まあなんだかんだ言って、承認欲求を満たしてくれる新しい相手を見つけただけなのかもしれない。


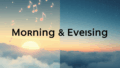
コメント